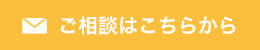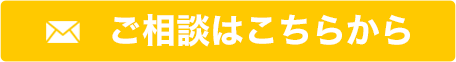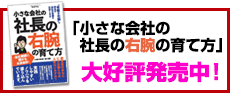第二創業と人材育成
2023年04月19日
株式会社ハッピーコンビの荒井幸之助です。
最近は何かと事業承継の仕事に関わることが多くなっています。
事業承継後に次期経営者が異なる分野に新規事業を展開することを「第二創業」と呼んだりします。
第二創業自体の意味は、広く現在とは異なる事業分野に展開することを意味しています。
最近は、事業承継で第二創業する経営者が増えているように見受けられます。
国は、事業承継・引き継ぎ補助金や事業再構築補助金等の施策で第二創業を応援しています。
しかし、当然に新たな事業展開にはリスクが伴います。
一般的に、リスクは既存事業との関連性が薄れるほどに高まります。
新規事業のリスクを減らすためには、新たな事業のノウハウの修得が必要です。
良くあるのは、フランチャイズに加盟して手軽にノウハウを獲得する方法です。
複数の異業種のフランチャイズに加盟して、多角化展開して稼いでいる会社があります。
そのご支援では、複数の事業をまとめたりコントロールするマネージャーの育成をしました。
実に要点を得た上手なお金の使い方、人の育て方をしていると感心しました。
また、外部からノウハウを得ずに独自にノウハウを得て展開する会社もあります。
その場合、新たな事業を担う人的資源の質が新規事業の結果を左右します。
中小企業の人材は限られているため、本業に並ぶような規模の新規事業を育てることには困難が伴います。
なので、中小企業の新規事業進出には後継者がその役目を担うことが多々あります。
良くあるのは、次期経営者が自ら外部の会社に修行に出たりして新たな事業のノウハウを身につける。
その後、会社に戻って新規事業を導入して育てていく。成長した新規事業が会社の本業に代わっていく・・。
こうして、会社は儲かる事業に新陳代謝されていくわけです。
でもこの新陳代謝は、本業が比較的長い期間継続できる条件があるときです。
現代は経営環境の変化がますます激しくなっています。
本業が持たない場合は、すぐに対処しなければいけません。
では中小企業として環境の変化にどうやって対応していけば良いのでしょうか。
それは、新規事業進出という大転換の手前に位置する新商品開発や新市場開拓で変化に対応することができます。
そのためには、それができる既存の人材を育成することが必要です。
つまり自立した人材、リーダ人材を増やす教育が必要です。
これからインフレの進行と共に人件費の高騰による人材獲得競争も激化するでしょう。
中小企業が優れた人材を採用することはますます難しくなると考えられます。
こそのため、中小企業にとっては、今いる人材の育成が企業の成長と継続の鍵になると考えています。